ヘリコバクター・ピロリ菌
ピロリ菌について
ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)は、胃の中にすみつく細菌の一種です。1980年代に発見されたこの菌は、胃酸という強い酸の中でも生きていける特殊な性質を持っており、長年にわたり人の胃の中で活動を続けることができます。
日本をはじめとするアジアの一部では特に感染率が高く、40歳以上の方では、2人に1人が感染しているともいわれています。近年では衛生環境の改善により、若い世代では感染者が減ってきています。胃がん等の原因となるため除菌治療が勧められます。
ピロリ菌の感染経路
ピロリ菌は、主に幼少期の生活環境を通じて感染すると考えられています。たとえば、①井戸水や不衛生な水からの感染、②家族間での食べ物の口移しや、箸の共有、③汚れた手や食器などを通じた経口感染、
などがあげられます。
ピロリ菌による体への影響
ピロリ菌は、胃の粘膜に炎症を引き起こします。この炎症が慢性的に続くことで、さまざまな病気の原因になります。以下は、ピロリ菌が関与する代表的な病気です。
1. 慢性胃炎(萎縮性胃炎)
ピロリ菌に感染すると、胃の粘膜にじわじわと炎症が起こり、粘膜が薄くなってしまいます。これを萎縮性胃炎といい、進行すると胃の防御力が弱まり、ほかの病気のリスクも高くなります。
2. 胃潰瘍・十二指腸潰瘍
胃や十二指腸の粘膜がただれて傷つく病気です。ピロリ菌が胃酸のバランスを崩すことで、潰瘍ができやすくなります。除菌治療を行うと再発を大きく減らせます。
3. 胃がん
ピロリ菌に長期間感染していると、胃の粘膜が変化して、胃がんのリスクが高まることがわかっています。特に、萎縮性胃炎や腸上皮化生がある方は要注意です。ピロリ菌を除菌することで、胃がんのリスクを下げることができると報告されています。
4. MALTリンパ腫
胃のリンパ組織にできる珍しいタイプの腫瘍ですが、ピロリ菌の除菌によって治癒することもあります。
ピロリ菌の検査方法
内視鏡検査で「ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎」と診断された人は、保険を使ってピロリ菌の検査・治療が可能です。ピロリ菌に感染しているかどうかを調べるために、以下のような検査が行われます。
〇尿素呼気試験:呼気(吐いた息)で調べる検査です。食事をして4時間以内の場合は検査できません。
〇抗体検査(血液・尿):ピロリ菌に対する抗体の有無を調べます。現在感染していなくても過去に感染していると陽性に出る事があるため、現時点での感染を有無を調べるためには使用できません。
〇便中抗原検査:便に含まれるピロリ菌のたんぱく質を調べます。
〇内視鏡検査と生検:胃カメラで胃の中の状態を見ながら、粘膜の一部を取って菌を調べる方法です。
検査方法は、症状や年齢、既往歴などによって選ばれます。
治療中の病気がある場合、内服薬(プロトンポンプ阻害薬)が検査結果に影響を与える可能性がありますので、すぐに検査ができないこともあります。まずは受診して医師に相談して下さい。
ピロリ菌の除菌治療
ピロリ菌に感染していることがわかったら、除菌治療を行います。これは、抗生物質と胃酸を抑える薬を1週間飲む治療です。多くの方が1回の治療で除菌に成功します(成功率は80〜90%)。万一失敗しても、薬を変更して再度治療を行えば、ほとんどの人で除菌が可能です。
治療の流れは次のようになります。
①ピロリ菌の感染が確認される
②除菌治療(1週間内服)
③治療終了から12週間以上経ってから、便中抗原検査、尿素呼気試験などで除菌成功の確認
※4~6週間で可能との報告もありますが確実な診断のため3ヶ月以降をお勧めしております
治療中は、抗生物質による軽い下痢や味覚異常などの副作用が出ることもありますが、ほとんどの場合は軽度です。
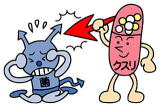
除菌後の注意点
ピロリ菌を除菌すると、胃潰瘍や胃がんのリスクを減らすことができます。ただし、すでに胃粘膜の萎縮や異常が進んでいる場合は、除菌後も胃がんのリスクが残ることがあります。そのため、除菌後も年に1回程度の胃カメラ検査を継続することが勧められています。
良くある質問(Q&A)
Q1. ピロリ菌とはどのような菌ですか?
A. 胃の強い酸の中でも生きることができる細菌です。主に幼少期に感染し、胃に棲みついて慢性的な炎症(胃炎)を引き起こします。放置すると胃潰瘍、十二指腸潰瘍、さらには胃がんの原因になることが分かっています。
Q2. ピロリ菌に感染しているか調べるには、どのような検査が必要ですか?
A. 検査方法にはいくつかあります。胃カメラの際に組織を採って調べる方法のほか、吐いた息を調べる「呼気テスト」、血液や尿、便を調べる方法などがあります。 ※保険診療でピロリ菌検査を行うには、法律上「胃カメラ検査を受けて胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍があることを確認すること」が必須条件となっています。
Q3. 除菌治療はどのように行いますか?
A. 2種類の「抗生物質」と、胃酸の分泌を抑える「胃薬」の合計3種類の薬を、1日2回、7日間服用します。正しく服用すれば、1回目の除菌(一次除菌)で約80〜90%の方が成功します。不成功だった場合でも、薬を変えて行う「二次除菌」が可能です。
Q4. 除菌治療中に気をつけることや、副作用はありますか?
A. 7日間、飲み忘れずに最後まで飲み切ることが最も重要です。途中でやめると菌が耐性を持ち、除菌が難しくなります。副作用として軟便や下痢、味覚異常などが現れることがありますが、多くは軽度です。ただし、激しい腹痛や血便、発疹が出た場合はすぐにご相談ください。
Q5. 除菌に成功すれば、もう胃がんの心配はありませんか?
A. 除菌によって胃がんになるリスクを大幅に下げることができますが、ゼロにはなりません。 特に感染期間が長かった方は、除菌後も胃粘膜にダメージが残っているため、早期発見のために定期的な胃カメラ検査を継続することが非常に大切です。
最後に
ピロリ菌は、発見されてからまだ数十年しか経っていませんが、私たちの健康に大きな影響を与えることがわかってきました。自覚症状がないまま感染している人も多く、気づかないうちに胃の粘膜がダメージを受けている可能性もあります。
40歳以上で一度もピロリ菌の検査を受けたことがない方、または胃の不調が続く方は、一度医師に相談することをおすすめします。早めに検査・治療を受けることで、大きな病気の予防につながります。
健康な胃を守るために、ピロリ菌のことを正しく理解し、必要な検査や治療を受けていきましょう。



